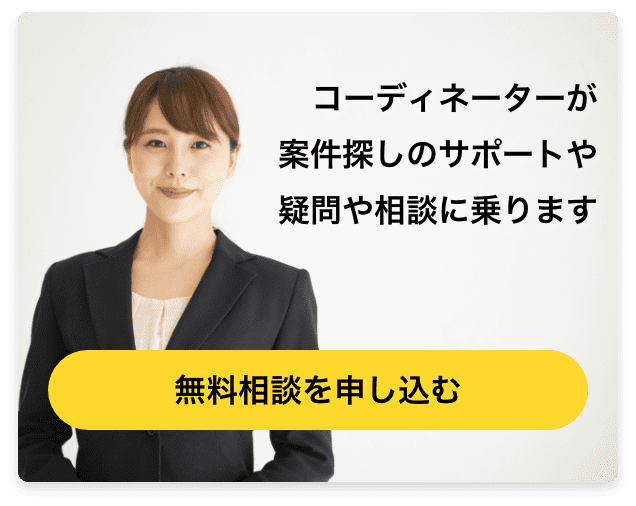フリーランスのエンジニアができる7つの節税対策|経費の計上もあわせて解説
Workteria(ワークテリア)では難易度の高いものから低いものまで、スキルや経験に合わせた案件を多数揃えています。会員登録は無料ですので、ぜひ会員登録してご希望の案件を探してみてください!
フリーランス/正社員のエンジニアとして活躍するには、ご自身のスキルや経験に合わせた仕事を選ぶことが大切です。ご希望の案件がみつからない場合はお気軽にお問い合わせください!ユーザ満足度の高いキャリアコンサルタントが在籍していますので、希望条件や悩み事などなんでもご相談ください。ご希望にピッタリの案件をご紹介させていただきます。
フリーランスができる節税対策はあるの?

フリーランスは利益の中から自分で税金を納めますが、利益をできるだけ残すために納める税金をいかに軽減するかが重要になってきます。
特に、これからフリーランスを目指している方にとって、フリーランスができる節税対策にはどのようなものがあるのか、事前に把握しておきたいところでしょう。
そして、節税対策を把握するために、まずはフリーランスが納める税金の種類を知ることが大切です。税金の内容を知ることで、節税対策の全容が把握しやすくなります。
フリーランスが納めなければならない税金

フリーランスは自分で税金を処理するため、何に対してどのような税金がかかるのかを知っておくことが必要です。
ここでは、フリーランスが納めなければならない税金について紹介します。
住民税
住民税とは市町村民税と道府県民税からなる地方税で、フリーランスの収入は住民税の対象です。納税する際は一括して各市町村に納付し、道府県民税は各市町村経由で道府県に支払われます。
住民税の額は、所得に応じて課せられる「所得割」と等しく課せられる「均等割」の合算です。所得割の税率は、前年度の課税所得金額に対して10%、均等割の税率は2022年現在で一律5,000円となっています。
住民税は確定申告に基づき計算され、市町村からの納税通知書を受け納付します。
出典:個人住民税|総務省
参照:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
出典:No.2020 確定申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
消費税
消費税とは商品やサービスに対して課せられる税金で、一般消費者が負担し、納税義務者である事業者が納付する間接税です。
フリーランスの場合、「基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合」もしくは「特定期間(前年の1月1日から6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合」に消費税の納税義務が発生しますが、フリーランス1年目は基準期間・特定期間ともに存在しないため消費税は免除されます。
納税義務があるフリーランスは1月から12月の納税額を算出し、翌年の3月31日までに消費税と地方消費税を併せて、所轄税務署に申告・納付します。
出典:消費税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
所得税
所得税は個人の所得に対してかかる税金であり、事業所得に該当するフリーランスの収入は所得税の対象です。
所得税額は「課税所得金額×税率-課税控除額」で算出され、フリーランスは確定申告により所得税を納付します。
上記計算式の「課税所得金額」とは、1年間の収入から必要経費と所得控除を差し引いたもので、「税率」および「課税控除額」は課税される所得金額に応じて7段階(5%から45%)に区分されています。
出典:所得税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
出典:出No.2020 確定申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
出典:No.2260 所得税の税率|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
個人事業税
個人事業税は個人が営む事業に課せられる税金で、都道府県に対して納付する地方税です。地方税の中でも都道府県が課税主体であるため、事務所・事業所がある都道府県税事務所が主な問い合わせ先になります。
フリーランスで個人事業税の対象となるのは、定められた業種のいずれかに該当し、所得が290万円を超えた場合です。
個人事業税の納税義務者へは、確定申告後に都道府県税事務所から納税通知書が送付されます。納付期限は、原則8月と11月の年2回です。
出典:個人事業税|神奈川県
参照:https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b004/index.html
出典:No.2020 確定申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
フリーランスのエンジニアができる7つの節税対策

ここまで、フリーランスが支払う税金についてみてきました。フリーランスとして独立した場合に支払い義務が発生する税金ですが、対策により税金の額を抑えることは可能です。
ここでは、フリーランスのエンジニアができる7つ節税対策について紹介します。
1:青色専従者給与の届出をしておく
フリーランスにとって専従者とは、フリーランスと生計を同じにしている15歳以上の親族で、1年のうち6ヶ月以上フリーランスの事業に専ら従事している家族従業員のことです。
通常、家族従業員に支払われる給与は経費とはなりませんが、青色申告で事前に「青色専従者給与の届出」をしているフリーランスは、家族従業員に支払った給与を全額経費にすることができるため節税効果が高まります。
ただし、配偶者を専従者とした場合に配偶者控除の対象から外れてしまうなど、専従者がそのほかの控除対象者である時は注意が必要です。どちらの方が節税効果を期待できるかはケースバイケースであるため、事前に税理士に相談することをおすすめします。
出典:[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
出典:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2:青色申告をする
青色申告とは、一定水準の記帳(複式簿記)に基づいて確定申告することにより、節税効果につながる有利な取扱いが受けられる制度のことです。
青色申告すると最大65万円(2022年現在)の控除を受けられる特別控除をはじめ、赤字を3年間にわたって繰り越せられる繰越控除といった制度を利用できます。
青色申告をするには、管轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出することが必要で、提出期限は青色申告を希望する年の3月15日です。フリーランスとなった年度から青色申告を希望する場合は、フリーランスとなってから2ヶ月以内の提出が必要となります。
出典:No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
3:ふるさと納税を利用する
ふるさと納税とは、故郷や応援したい自治体に寄付した場合、寄付額のうち2,000円を超える部分について所得税および住民税から原則として全額控除されるうえに、自治体からの返礼品を受け取れる制度です。
ただし、ふるさと納税の控除額には上限があり、上限額を超えた金額は自己負担となるため、上限額を超えないように寄付することが節税のポイントです。
フリーランスがふるさと納税の控除を受けるには、ふるさと納税した翌年の確定申告で寄付金控除の欄に「寄付金受領証明書」の金額を記入する必要があります。
出典:よくわかる!ふるさと納税|総務省
参照:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/
出典:No.2020 確定申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
4:控除を計上する
所得税を算出する際の税率は所得額が多いほど高くなるため、所得控除により所得額を少なくすることで所得税を抑えられます。
つまり、控除を計上することは節税対策の一環であり、確定申告における大切なポイントです。
確定申告書には各種控除欄がありますが、以下にフリーランスが有益に利用できる控除について紹介します。
出典:No.2260 所得税の税率|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
所得控除
所得控除とは、控除の要件に該当する場合に所得から一定額を差し引ける制度で、所得税の計算時に納税者の個人的事情を加味することが目的です。
所得控除として生命保険控除や医療費控除、配偶者控除、基礎控除などが設けられており、各種控除により課税対象となる所得金額を減らすことができます。
出典:No.1100 所得控除のあらまし|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
税額控除
税額控除とは、算出した所得税額(納税額)から一定の金額を控除する制度で、税額から直接控除できるというものです。
税額控除として、配当控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など、さまざまな控除が設けられています。
出典:No.1200 税額控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm
確定拠出型年金
確定拠出年金は、月々の掛金と金融商品(投資信託や定期預金など)で運用した運用収益との合計額を基に、将来の給付額が決定する年金制度です。
フリーランスが確定拠出年金の加入者である場合、拠出した掛金は全額所得控除の対象となります。
出典:確定拠出年金制度の概要|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html#205
小規模企業共済
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)によって運営される共済制度で、小規模企業の経営者やフリーランスなどのための退職金制度です。
フリーランスが小規模企業共済に加入している場合、掛金の全額が所得控除できます。
出典:小規模企業共済|中小機構
参照:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
国民年金保険料
フリーランスが加入する国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象となり、国民年金保険料の全額を所得から控除できます。
また、自己と生計を同一にする家族の国民年金保険料を支払っている場合は、その金額も含めて控除を受けることが可能です。
出典:No.1130 社会保険料控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
出典:国民年金保険料|国民年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html
5:経費を計上する
フリーランスが経費(事業のために要した費用)を計上するメリットは、節税対策です。
課税所得額(課税される所得額)は「1年間の収入-必要経費-所得控除」となるため、所得控除同様、経費を計上することで所得税を抑えられます。経費に該当するかどうかの判断基準は、「事業に関係しているか」「売り上げに貢献しているか」の2点です。
フリーランスの開業にかかった費用(開業費)も経費として計上できるため、開業準備中の方は開業前の領収証も保管することをおすすめします。
出典:No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
出典:所得税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
6:減価償却の特例を利用する
減価償却の特例とは、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の略称で、フリーランスも対象者となりますが、青色申告をしているフリーランスに限られます。
通常、高額で長期にわたって利用する減価償却資産は、購入時に経費として計上するのではなく何年かに分けて計上されます。
しかし、減価償却の特例では30万円未満の減価償却資産を購入時(平成18年4月1日~令和4年3月31日までの間)、一定の要件の基に、その取得価額相当を経費として算入できます。
この特例の適用を受けるためには、確定申告書時に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要です。
出典:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
7:事業が発展したら法人化にする
フリーランスが納税する所得税は所得が増えると税率が高くなるため、事業が発展したら法人化するというのも税負担を少なくする手段です。
税率の関係上、法人税の方が節税になるからですが、以下に「法人税の税率」と「個人税の税率」について紹介します。
法人税の税率の場合
法人税の税率は中小法人の場合、所得金額800万円までは15%、超える金額については23%程度と、2段階だけの区分となっています。
所得金額が800万円では一律15%であるため、所得金額が400万円であっても800万円であっても税率は同じ15%です。
出典:No.5759 法人税の税率|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
所得税の税率の場合
所得税の税率は5%から45%の7段階で、所得が高いほど税率が高くなる累進課税制度を採用しています。
所得金額により税率が変わり、例えば、所得金額が400万円の税率は20%、800万円の税率は23%です。
出典:No.2260 所得税の税率|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
フリーランスが節税する時に気を付けること

フリーランスにとって節税とは、事業を営むうえで必要不可欠な事項ですが、節税により不利になってしまうこともあります。
ここでは、フリーランスが節税する時に気を付けることについて紹介します。
節税をやりすぎると審査が通らない
クレジットカードや住宅ローンを申し込む際の年収について、会社員などは税込年収(税金・社会保険料が控除される前の金額)を記入するのに対し、フリーランスの場合は経費控除後の金額を年収として記入します。
そのため、節税しすぎると所得が減り、クレジットカードや住宅ローンの審査が通らない可能性もでてきます。
経費の計上をやりすぎないようにする
経費の計上は節税のために大切ですが、経費の計上をやりすぎるとフリーランスも法人と同様に税務調査が行われる可能性があります。
経費はあくまでも事業のために要した費用であることを認識し、事業に関係のないものを経費に計上しないよう注意しましょう。
フリーランスになる前に節税対策の勉強をしておこう

給与から税金が天引きされる会社員と異なり、フリーランスは自分で税金を納付することになるため、税金についての知識が必要です。
知識があれば、経費や減価償却といった項目を上手く活用して、フリーランスになった年から税金の負担を軽減することができます。
フリーランスになり、日々の事業に追われて税金のことが後回しにならないよう、フリーランスになる前に節税対策の勉強をしておきましょう。
【著者】
東京ITカレッジで講師をしています。
Java 大好き、どちらかというと Web アプリケーションよりもクライアントアプリケーションを好みます。でも、コンテナ化は好きです。Workteria(旧 Works)ではみなさまのお役に立つ情報を発信しています。
「Workteria」「東京ITカレッジ」をご紹介いただきました!
正社員/フリーランスの方でこのようなお悩みありませんか?
- 自分に合う案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な案件探し・契約周りは任せて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、Workteriaサイトをご利用ください!
定期的にご本人に合う高額案件を紹介
リモートワークなど自由な働き方ができる案件多数
専属エージェントが契約や請求をトータルサポート